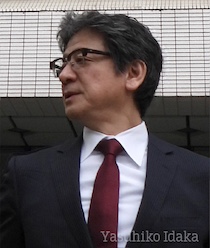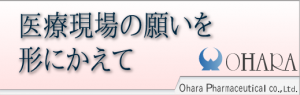【7月10日発】 業界要望「手ごたえ有り」 中医協薬価部会は殆ど反論無しで“静聴” 26年度改革

◆かつての中医協薬価専門部会
26年4月の薬価制度改革に向け、医薬品業界団体が9日、厚労省の中央社会保険医療協議会薬価専門部会で意見陳述した。研究開発型企業で構成される日米欧3団体は特許期間中の医薬品について「薬価維持」などを
求めた。また、後発品企業で構成される日本ジェネリック製薬協会(JGA)は、薬価が低い品目の供給が、物価上昇などの影響を受け厳しさを増していることを強調、該当品の薬価引き上げを求めた。中医協委員から業界の意見を押し返すような強い言動は無かった。まだ議論は序盤戦――。参院選後に政局を迎える可能性もあり、今回は“聞き置いた”という感じだ。会議は終始、穏やかに進行した。
製薬業界は新薬の薬価について「収載時」と「収載後の改定」に分けて提案した。
「収載時」は、類似薬の薬価を基に算定する「類似薬効比較方式」が原則だが、類似薬選定の基準が厳しいので、画期的新薬は類似薬が見つからず「原価計算方式」(原価プラス加算)で算定されるケースが多い。しかし、原価計算方式の場合は、原価の開示度合いに応じて加算額を削ることになっている。開示度が高ければ加算は多く、低ければ少なくなる。そのため真に画期的で有用性な新薬でも原価の開示が不十分だと、評価は控えめになる。画期的新薬は、原材料などの調達で複数の企業、国に跨ることが多く、原価の内訳を精密に開示するのは難しい。
そこで業界は類似薬選定の基準を見直すよう求めた。
今は、効能効果、薬理作用、化学構造式、投与形態・用法で類似薬を決めるが、新たに「疾患特性」や「製剤特性」を加え、類似薬選定を柔軟にするよう訴えた。
「収載後の改定」は①特許期間中の医薬品の「薬価維持」②特例拡大再算定の廃止③市場拡大再算定での「共連れ」の廃止――の3点を求めた。
既報の通り、今年の「骨太の方針」は薬価制度について厳しい方針をほとんど書き込んでいない。こんなことは珍しい。ここは攻め時――。業界が要望する「収載時」「収載後の改定」に関する要望が実現する可能性も高い。
米国研究製薬工業協会のシモーネ・トムセン在日執行委員会委員長が日本の薬価制度を取り巻く「新たなリスク」として「米大統領令」を上げた。
米トランプ氏が発した大統領令では、輸入医薬品は世界で最も低い薬価(最恵国待遇薬価)でしか購入しない方針を示している。実際にいつから、どういう範囲で実施するのか不明だが、かりに日本で低い薬価を付けると、将来、連動して米国での価格が下がる可能性がある。シモーネ氏は、そこを強調し、業界要望の実現を迫った。
◆“バイオAG”や“逆ザヤ”対策も課題に
そのほか日本バイオシミラー協議会が、バイオAG(オーソライズドジェネリック)対策を訴えた。バイオAGはオリジナル新薬企業が他社に権利を譲渡して、その企業が特許切れ前に販売するバイオ薬を指す。協議会は、バイオAGがバイオシミラーの開発、普及を阻害すると指摘、薬価政策上、何らかの対策を求めた。
日本医薬品卸業連合会は、薬価が低いにもかかわらず、メーカーが仕切価格を上げる品目があり、「流通コストが吸収できない」と窮状を訴えた。
診療側の薬剤師会委員からも、低薬価品で購入価が薬価を上回る“逆ザヤ”現象がかなりの割合で生じており、「このままでは医療機関、薬局の経営が立ち行かなくなる」とし、厚労省に「しっかり対応をお願いしたい」と訴える場面もあった。
【意見陳述者は以下】日本製薬団体連合会会長・安川 健▽日本ジェネリック製薬協会 会長・川俣 知己▽日本製薬工業協会会長・宮柱 明日香▽米国研究製薬工業協会在日執行委員会委員長・シモーネ・トムセン▽欧州製薬団体連合会会長・岩屋 孝彦▽再生医療イノベーションフォーラム副会長・廣瀬徹▽日本バイオシミラー協議会会長・島田博史▽ 日本バイオテク協議会会長・森 敬太▽日本医薬品卸売業連合会会長・宮田 浩美 (敬称略)