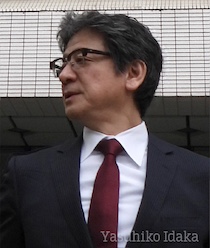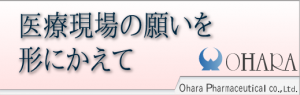Posted on 2月 26th, 2026 by IDAKA

第2次高市早苗内閣発足後、初の衆院代表質問(2月25日)で、国民民主党の玉木雄一郎代表が薬価改定について質問したが、高市首相にそつなく交わされ、とくに新たな見解を引き出すことはできなかった。
そもそも玉木代表の質問自体、踏み込みが浅かった。提案実現に向けた迫力にも欠けていた。この答弁に限って言えば、医薬品流通改善や中間年改定について、高市内閣が大きな政策的な転換を進める気配は感ぜられなかった。

先の衆院選で自民党が歴史的な大勝を収め、高市内閣について「長期政権化するのではないか」との見方も出ている。かりにそうなれば、長年手付かずだった懸案の課題をじっくり議論し、新ステージに駒を進めるチャンスもあるのではないかと、私は考えた。しかし、こと医薬品流通や、薬価改定については、いまのところその気配はない。先週2月19日、薬価流通政策研究会・くすり未来塾の記者会見があって武田俊彦共同代表に、
Posted on 2月 25th, 2026 by IDAKA


◆MR認定センターの近澤洋平専務理事(右)、小日向強事務局長・企画部長(左)
MR認定センターが数年がかりで作り上げた新たな「MR認定制度」が26年4月からスタートする。所属企業任せではなく、個々人が自律性を持って試験を受け、合格後も学習に取り組めるよう試験・教育システムを組み替える。また、企業が自社MRの質を担保するために実施する「実務教育」について、センター側から統一の基準を提示。公的な信頼性をこれまで以上に高める。今回の新制度は「1997年のセンター設立以来、最大の改革」(近澤洋平専務理事)―。2月18日に東京、20日に大阪で開いた毎年恒例の講習会で新制度について改めて説明。会場では例年以上に熱を帯びた多くの質疑があった。
新しい認定制度は
Posted on 2月 20th, 2026 by IDAKA

日本製薬工業協会が年2回開く会長記者会見が19日あった。
宮柱明日香会長が登壇し、現状認識、課題、取り組みの進捗状況などを総花的に説明したが、今回とくに
Posted on 2月 13th, 2026 by IDAKA
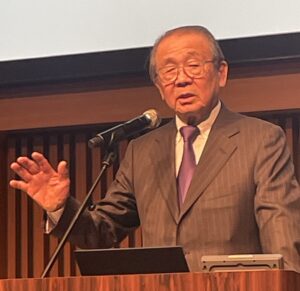
◆中外製薬・永山治名誉会長
AI(人工知能)を使って薬を生み出すー!いわゆるAI創薬という言葉が使われるようになって久しい。しかし、ここでも「欧米や中国に比べ、日本は遅れている」と言われている。そんな中、2003年創業のFRONTEOが自社開発したAI「KIBIT(キビット)」が製薬企業の創薬分野で注目され、ここ数年、契約件数を伸ばしている。すでに中外製薬、第一三共、エーザイ、MeijiSeikaファルマほか、アカデミアなどと10を超えるプロジェクトが進行している。それは
Posted on 2月 9th, 2026 by IDAKA
 高市早苗政権、自民党の圧倒的な勝利で衆院選は終わった。自民党だけで、単独過半数どころか3分の2を超える議席を獲得。逆に言えば野党の議席は3分の1に満たない。しかも野党は皆、小粒で分立している。極端な話、高市政権、自民党内で政策を立案し、強く押し込めば、そのまま通る。で社会保障、医療保険、薬価政策がこの先、どうなるかーー。おそらく、
高市早苗政権、自民党の圧倒的な勝利で衆院選は終わった。自民党だけで、単独過半数どころか3分の2を超える議席を獲得。逆に言えば野党の議席は3分の1に満たない。しかも野党は皆、小粒で分立している。極端な話、高市政権、自民党内で政策を立案し、強く押し込めば、そのまま通る。で社会保障、医療保険、薬価政策がこの先、どうなるかーー。おそらく、
Posted on 2月 5th, 2026 by IDAKA

 武田薬品工業が京都大学iPS細胞研究所との産学共同研究(T- CiRAプログラム)から25年度末で手を引く。非常に複雑な思いだ。iPS細胞は画期的かつ偉大な発見だが、そもそも臨床応用にはいくつものハードルがあり、そう簡単ではない。医薬品、医療技術は基礎から臨床応用につなげるまで膨大な時間と資金を要する。iPS細胞も当初からそういわれていた。10年前(2016年)、そこに武田が手を差し伸べた。しかし、新薬や治療技術など臨床的な果実を手にするまでには至らず。今回、手を引くことになった。武田に対しては「一企業でよくぞこれまで続けてきた」と賛辞を贈りたい。しかし、一方、
武田薬品工業が京都大学iPS細胞研究所との産学共同研究(T- CiRAプログラム)から25年度末で手を引く。非常に複雑な思いだ。iPS細胞は画期的かつ偉大な発見だが、そもそも臨床応用にはいくつものハードルがあり、そう簡単ではない。医薬品、医療技術は基礎から臨床応用につなげるまで膨大な時間と資金を要する。iPS細胞も当初からそういわれていた。10年前(2016年)、そこに武田が手を差し伸べた。しかし、新薬や治療技術など臨床的な果実を手にするまでには至らず。今回、手を引くことになった。武田に対しては「一企業でよくぞこれまで続けてきた」と賛辞を贈りたい。しかし、一方、
Posted on 1月 28th, 2026 by IDAKA

衆院選がスタートの火ぶたを切った。長く続いた自民党・公明党連立が昨秋、“破局”、自民が新たに日本維新の会(以下、維新)と連立を組み、野党第一党の立憲民主党が公明党と新党「中道改革連合」(中道)を立ち上げた。その時点で何十年も続き、ある種、常態化していた与野党の政治力学は公式を失った。結果がどうなるかーー。混迷を深めている。何人かの識者に話を聞いたが、皆、「フタを開けてみなければわからない」「全く読めない」と口を揃える。果たして選挙後、医療、医薬品政策はどう変わるか?
Posted on 1月 21st, 2026 by IDAKA

◆東和薬品の吉田逸郎代表取締役社長
後発品事業の大手、東和薬品が大塚製品と医薬品製造で協業すると発表した(1月21日付)。長期収載品や後発医薬品の品不足が度々起こる中、ここに来て各社が協力して何とかしようという動きが顕在化してきた。昨年はMeijiSeikaファルマの「新・コンソーシアム構想」によるダイトとの協業、沢井製薬と日医工の協業発表があり、今度の東和、大塚の協業で大きく3つの潮流ができた。「そろそろ東和が
Posted on 1月 16th, 2026 by IDAKA
 衆院の解散総選挙が決定的となった。今なぜ選挙なのかーー。 諸説あるが、人気が高いうちに選挙で大勝を収め、盤石な長期政権を築きたいー。高市早苗首相が、そう考えたというのが最もシンプルな説だ。24年秋、石破茂前政権が発足後すぐに「裏金問題について国民の信を問う」との理由で、衆院選を実施して自民党は大敗、現在、日本維新の会と連立を組んで議席はギリギリ過半数の233(自民199、維新34)という心もとない状況だ。高市首相が選挙で大勝して単独過半数以上を獲得したいと考えて何も不思議はない。各種メディアの世論調査によると、確かに高市政権は発足後、高支持率が続いている。しかし、今、衆院選を打って、本当に大勝できるかーー。解散総選挙を公にしたとたん、そう簡単ではない状況が形成されてきている。政財官の実務者に意見を聞くと、選挙後も自民党が最大与党(最も議席が多い与党)を維持する、というところまでの見方は概ね共通しているものの、「“大勝”とまではいかないのでは」との声が多い。それどころか、「議席数を
衆院の解散総選挙が決定的となった。今なぜ選挙なのかーー。 諸説あるが、人気が高いうちに選挙で大勝を収め、盤石な長期政権を築きたいー。高市早苗首相が、そう考えたというのが最もシンプルな説だ。24年秋、石破茂前政権が発足後すぐに「裏金問題について国民の信を問う」との理由で、衆院選を実施して自民党は大敗、現在、日本維新の会と連立を組んで議席はギリギリ過半数の233(自民199、維新34)という心もとない状況だ。高市首相が選挙で大勝して単独過半数以上を獲得したいと考えて何も不思議はない。各種メディアの世論調査によると、確かに高市政権は発足後、高支持率が続いている。しかし、今、衆院選を打って、本当に大勝できるかーー。解散総選挙を公にしたとたん、そう簡単ではない状況が形成されてきている。政財官の実務者に意見を聞くと、選挙後も自民党が最大与党(最も議席が多い与党)を維持する、というところまでの見方は概ね共通しているものの、「“大勝”とまではいかないのでは」との声が多い。それどころか、「議席数を
Posted on 1月 15th, 2026 by IDAKA
 衆院の解散総選挙が決定的となった。高市早苗政権の業界評価はどうか?選挙後、医療、製薬産業政策への影響はどう出るか?まずは高市現政権について――。発足してまだ数か月だが、敢えて業界関係者に聞くと、
衆院の解散総選挙が決定的となった。高市早苗政権の業界評価はどうか?選挙後、医療、製薬産業政策への影響はどう出るか?まずは高市現政権について――。発足してまだ数か月だが、敢えて業界関係者に聞くと、










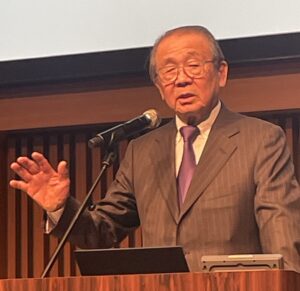
 高市早苗政権、自民党の圧倒的な勝利で衆院選は終わった。自民党だけで、単独過半数どころか3分の2を超える議席を獲得。逆に言えば野党の議席は3分の1に満たない。しかも野党は皆、小粒で分立している。極端な話、高市政権、自民党内で政策を立案し、強く押し込めば、そのまま通る。で社会保障、医療保険、薬価政策がこの先、どうなるかーー。おそらく、
高市早苗政権、自民党の圧倒的な勝利で衆院選は終わった。自民党だけで、単独過半数どころか3分の2を超える議席を獲得。逆に言えば野党の議席は3分の1に満たない。しかも野党は皆、小粒で分立している。極端な話、高市政権、自民党内で政策を立案し、強く押し込めば、そのまま通る。で社会保障、医療保険、薬価政策がこの先、どうなるかーー。おそらく、
 武田薬品工業が京都大学iPS細胞研究所との産学共同研究(T- CiRAプログラム)から25年度末で手を引く。非常に複雑な思いだ。iPS細胞は画期的かつ偉大な発見だが、そもそも臨床応用にはいくつものハードルがあり、そう簡単ではない。医薬品、医療技術は基礎から臨床応用につなげるまで膨大な時間と資金を要する。iPS細胞も当初からそういわれていた。10年前(2016年)、そこに武田が手を差し伸べた。しかし、新薬や治療技術など臨床的な果実を手にするまでには至らず。今回、手を引くことになった。武田に対しては「一企業でよくぞこれまで続けてきた」と賛辞を贈りたい。しかし、一方、
武田薬品工業が京都大学iPS細胞研究所との産学共同研究(T- CiRAプログラム)から25年度末で手を引く。非常に複雑な思いだ。iPS細胞は画期的かつ偉大な発見だが、そもそも臨床応用にはいくつものハードルがあり、そう簡単ではない。医薬品、医療技術は基礎から臨床応用につなげるまで膨大な時間と資金を要する。iPS細胞も当初からそういわれていた。10年前(2016年)、そこに武田が手を差し伸べた。しかし、新薬や治療技術など臨床的な果実を手にするまでには至らず。今回、手を引くことになった。武田に対しては「一企業でよくぞこれまで続けてきた」と賛辞を贈りたい。しかし、一方、
 衆院の解散総選挙が決定的となった。今なぜ選挙なのかーー。 諸説あるが、人気が高いうちに選挙で大勝を収め、盤石な長期政権を築きたいー。高市早苗首相が、そう考えたというのが最もシンプルな説だ。24年秋、石破茂前政権が発足後すぐに「裏金問題について国民の信を問う」との理由で、衆院選を実施して自民党は大敗、現在、日本維新の会と連立を組んで議席はギリギリ過半数の233(自民199、維新34)という心もとない状況だ。高市首相が選挙で大勝して単独過半数以上を獲得したいと考えて何も不思議はない。各種メディアの世論調査によると、確かに高市政権は発足後、高支持率が続いている。しかし、今、衆院選を打って、本当に大勝できるかーー。解散総選挙を公にしたとたん、そう簡単ではない状況が形成されてきている。政財官の実務者に意見を聞くと、選挙後も自民党が最大与党(最も議席が多い与党)を維持する、というところまでの見方は概ね共通しているものの、「“大勝”とまではいかないのでは」との声が多い。それどころか、「議席数を
衆院の解散総選挙が決定的となった。今なぜ選挙なのかーー。 諸説あるが、人気が高いうちに選挙で大勝を収め、盤石な長期政権を築きたいー。高市早苗首相が、そう考えたというのが最もシンプルな説だ。24年秋、石破茂前政権が発足後すぐに「裏金問題について国民の信を問う」との理由で、衆院選を実施して自民党は大敗、現在、日本維新の会と連立を組んで議席はギリギリ過半数の233(自民199、維新34)という心もとない状況だ。高市首相が選挙で大勝して単独過半数以上を獲得したいと考えて何も不思議はない。各種メディアの世論調査によると、確かに高市政権は発足後、高支持率が続いている。しかし、今、衆院選を打って、本当に大勝できるかーー。解散総選挙を公にしたとたん、そう簡単ではない状況が形成されてきている。政財官の実務者に意見を聞くと、選挙後も自民党が最大与党(最も議席が多い与党)を維持する、というところまでの見方は概ね共通しているものの、「“大勝”とまではいかないのでは」との声が多い。それどころか、「議席数を 衆院の解散総選挙が決定的となった。高市早苗政権の業界評価はどうか?選挙後、医療、製薬産業政策への影響はどう出るか?まずは高市現政権について――。発足してまだ数か月だが、敢えて業界関係者に聞くと、
衆院の解散総選挙が決定的となった。高市早苗政権の業界評価はどうか?選挙後、医療、製薬産業政策への影響はどう出るか?まずは高市現政権について――。発足してまだ数か月だが、敢えて業界関係者に聞くと、