Posted on 7月 10th, 2025 by IDAKA

◆かつての中医協薬価専門部会
26年4月の薬価制度改革に向け、医薬品業界団体が9日、厚労省の中央社会保険医療協議会薬価専門部会で意見陳述した。研究開発型企業で構成される日米欧3団体は特許期間中の医薬品について「薬価維持」などを 会員の方はコチラをクリック »
Posted on 7月 4th, 2025 by IDAKA
 日本の政治はしばらく安定しない。長きに渡る自民・公明連立政権が揺らいでいるほか、米の第二次トランプ政権が「自国優先主義」を強め、同盟国、日本にも容赦なく新たな要求を突き付けている。「安定しない」、すなわち「不安定な状況」は、必ずしもネガティブなことではない。物事を変えたり、生み出すには好機だ。医薬品の研究開発、薬価政策もしかり。成長を志向するなら現状維持は許されない。揺らぐ情勢にいかに向き合うかーー。製薬業界も構想力、交流力、交渉力、説得力が問われる。今、米国との関税交渉絡みで自動車業界が見えるところ、見えないところ含め、かつてないほど高度で精密なロビイングを展開している。製薬業界も動く時だ。
日本の政治はしばらく安定しない。長きに渡る自民・公明連立政権が揺らいでいるほか、米の第二次トランプ政権が「自国優先主義」を強め、同盟国、日本にも容赦なく新たな要求を突き付けている。「安定しない」、すなわち「不安定な状況」は、必ずしもネガティブなことではない。物事を変えたり、生み出すには好機だ。医薬品の研究開発、薬価政策もしかり。成長を志向するなら現状維持は許されない。揺らぐ情勢にいかに向き合うかーー。製薬業界も構想力、交流力、交渉力、説得力が問われる。今、米国との関税交渉絡みで自動車業界が見えるところ、見えないところ含め、かつてないほど高度で精密なロビイングを展開している。製薬業界も動く時だ。
次の参院選(7月20日投票、改選議席124)における自民、公明の獲得議席目標は「最低50」と
Posted on 7月 1st, 2025 by IDAKA
 製薬企業の情報提供、販売促進などの業務を受託するCSO(Contract Sales Organization=医薬品販売業務受託機関)のビジネスに変化の波が出てきた。日本CSO協会(以下、CSO協会)が公表した最新の実態調査結果(24年10月時点の実態)によると、会員各社(CSO)が契約、派遣などの形態で製薬企業などに送り込んだ人員総数は前期調査(23年10月時点の実態)との比較でわずかながら減少した。【写真=CSO協会の昌原清植会長(前列中央)、八所孝志副会長(前列右端)ほか加盟企業代表】。この先、横ばいで推移するのか、盛り返す(再び増加する)のか、減少し続けるのかー。まだわからない。ただ、CSOを活用する事業者の構成割合や、ニーズに変化が出始めており、
製薬企業の情報提供、販売促進などの業務を受託するCSO(Contract Sales Organization=医薬品販売業務受託機関)のビジネスに変化の波が出てきた。日本CSO協会(以下、CSO協会)が公表した最新の実態調査結果(24年10月時点の実態)によると、会員各社(CSO)が契約、派遣などの形態で製薬企業などに送り込んだ人員総数は前期調査(23年10月時点の実態)との比較でわずかながら減少した。【写真=CSO協会の昌原清植会長(前列中央)、八所孝志副会長(前列右端)ほか加盟企業代表】。この先、横ばいで推移するのか、盛り返す(再び増加する)のか、減少し続けるのかー。まだわからない。ただ、CSOを活用する事業者の構成割合や、ニーズに変化が出始めており、
Posted on 6月 26th, 2025 by IDAKA
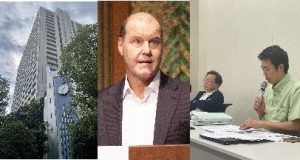 昨日6月25日は中央社会保険医療協議会・薬価専門部会、武田薬品工業の株主総会、日本維新の会の社会保険料引き下げに関するメディアセミナーがあった。いつものように事実を歪めない範囲で独断と私見を交えてレポートする。
昨日6月25日は中央社会保険医療協議会・薬価専門部会、武田薬品工業の株主総会、日本維新の会の社会保険料引き下げに関するメディアセミナーがあった。いつものように事実を歪めない範囲で独断と私見を交えてレポートする。
Posted on 6月 20th, 2025 by IDAKA

◆「がんばらないと取り負ける」と日本製薬団体連合会の宮島俊彦理事長
政府がまとめた骨太の方針(経済財政運営と改革の基本方針)2025は例年と比べ極めて“地雷”が少ない。副題は~「今日より明日はよくなる」と実感できる社会へ~。中学、高校の文化祭テーマのようで、昭和生まれの私は何となくこそばゆさを覚える。7月20日の参院選、その前哨戦となる東京都議選(6月22日)を前に、与党の支持率はいまひとつ伸びない。その影響もあってのことだろうか。医薬品関連の施策を見ても業界に風圧を及ぼす
Posted on 6月 18th, 2025 by IDAKA
本日、開催する予定となっていた中医協薬価専門部会は中止となりました。17日夕方まで予定表に載っていましたが、取りやめになりました。当局は「諸般の事情により」としています。
Posted on 6月 17th, 2025 by IDAKA

◆日薬連・保険薬価研の藤原尚也委員長(中外製薬執行役員・渉外調査担当)
26年4月の薬価制度改革に向けた論議が始まる。
明日18日、4月以降初の中央社会保険医療協議会・薬価専門部会の開催が予定されている。例年通りなら改定の「主な課題」と「議論の進め方」を決める“キックオフミーティング”となる。今回は、検討課題に、これまでとは違った
Posted on 6月 12th, 2025 by IDAKA
 アッヴイ合同会社は日本のスタートアップ企業や研究グループなどを対象に同社の研究施設を貸与したり、賞金を授与する「アッヴィ・ジャパン・イノベーション・アワード」(以下、アワード)を開始する。ディアゴ・カンボス ロドリゲス社長【写真右】が11日の定例記者会見「ビジネスアップデート2025」に初登壇(昨年11月就任)、「外資系日本法人として、日本のイノベーションを牽引、貢献していく必要が
アッヴイ合同会社は日本のスタートアップ企業や研究グループなどを対象に同社の研究施設を貸与したり、賞金を授与する「アッヴィ・ジャパン・イノベーション・アワード」(以下、アワード)を開始する。ディアゴ・カンボス ロドリゲス社長【写真右】が11日の定例記者会見「ビジネスアップデート2025」に初登壇(昨年11月就任)、「外資系日本法人として、日本のイノベーションを牽引、貢献していく必要が
Posted on 6月 5th, 2025 by IDAKA
 次の参院選に向け、与野各党が本格的に準備を進めている。自民党は石破茂政権発足直後から、というかその前の岸田文雄政権から支持率が落ち込んだまま。いかに野党に流れる票を抑えダメージを最小限にするかー。いわば防戦だ。しかし、ここに来て野党の中で高く評価されていた国民民主党の支持率が急落。自民からすれば
次の参院選に向け、与野各党が本格的に準備を進めている。自民党は石破茂政権発足直後から、というかその前の岸田文雄政権から支持率が落ち込んだまま。いかに野党に流れる票を抑えダメージを最小限にするかー。いわば防戦だ。しかし、ここに来て野党の中で高く評価されていた国民民主党の支持率が急落。自民からすれば
Posted on 6月 3rd, 2025 by IDAKA
 日本で一時激減した子宮頸がん(HPV)ワクチンの接種率がここ数年、回復基調にある。ただ、実施主体である都道府県別に見ると、最上位と最下位に倍以上の開きがあり、普及、浸透の地域格差が浮き彫りになっている。MSDのカイル・タトル代表取締役社長【右写真】は「居住地によって接種機会が変わってしまうのはよくない。格差を
日本で一時激減した子宮頸がん(HPV)ワクチンの接種率がここ数年、回復基調にある。ただ、実施主体である都道府県別に見ると、最上位と最下位に倍以上の開きがあり、普及、浸透の地域格差が浮き彫りになっている。MSDのカイル・タトル代表取締役社長【右写真】は「居住地によって接種機会が変わってしまうのはよくない。格差を


 日本の政治はしばらく安定しない。長きに渡る自民・公明連立政権が揺らいでいるほか、米の第二次トランプ政権が「自国優先主義」を強め、同盟国、日本にも容赦なく新たな要求を突き付けている。「安定しない」、すなわち「不安定な状況」は、必ずしもネガティブなことではない。物事を変えたり、生み出すには好機だ。医薬品の研究開発、薬価政策もしかり。成長を志向するなら現状維持は許されない。揺らぐ情勢にいかに向き合うかーー。製薬業界も構想力、交流力、交渉力、説得力が問われる。今、米国との関税交渉絡みで自動車業界が見えるところ、見えないところ含め、かつてないほど高度で精密なロビイングを展開している。製薬業界も動く時だ。
日本の政治はしばらく安定しない。長きに渡る自民・公明連立政権が揺らいでいるほか、米の第二次トランプ政権が「自国優先主義」を強め、同盟国、日本にも容赦なく新たな要求を突き付けている。「安定しない」、すなわち「不安定な状況」は、必ずしもネガティブなことではない。物事を変えたり、生み出すには好機だ。医薬品の研究開発、薬価政策もしかり。成長を志向するなら現状維持は許されない。揺らぐ情勢にいかに向き合うかーー。製薬業界も構想力、交流力、交渉力、説得力が問われる。今、米国との関税交渉絡みで自動車業界が見えるところ、見えないところ含め、かつてないほど高度で精密なロビイングを展開している。製薬業界も動く時だ。 製薬企業の情報提供、販売促進などの業務を受託するCSO(Contract Sales Organization=医薬品販売業務受託機関)のビジネスに変化の波が出てきた。日本CSO協会(以下、CSO協会)が公表した最新の実態調査結果(24年10月時点の実態)によると、会員各社(CSO)が契約、派遣などの形態で製薬企業などに送り込んだ人員総数は前期調査(23年10月時点の実態)との比較でわずかながら減少した。【写真=CSO協会の昌原清植会長(前列中央)、八所孝志副会長(前列右端)ほか加盟企業代表】。この先、横ばいで推移するのか、盛り返す(再び増加する)のか、減少し続けるのかー。まだわからない。ただ、CSOを活用する事業者の構成割合や、ニーズに変化が出始めており、
製薬企業の情報提供、販売促進などの業務を受託するCSO(Contract Sales Organization=医薬品販売業務受託機関)のビジネスに変化の波が出てきた。日本CSO協会(以下、CSO協会)が公表した最新の実態調査結果(24年10月時点の実態)によると、会員各社(CSO)が契約、派遣などの形態で製薬企業などに送り込んだ人員総数は前期調査(23年10月時点の実態)との比較でわずかながら減少した。【写真=CSO協会の昌原清植会長(前列中央)、八所孝志副会長(前列右端)ほか加盟企業代表】。この先、横ばいで推移するのか、盛り返す(再び増加する)のか、減少し続けるのかー。まだわからない。ただ、CSOを活用する事業者の構成割合や、ニーズに変化が出始めており、