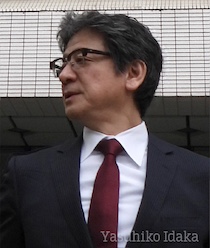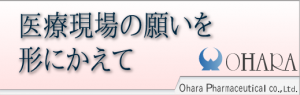Posted on 1月 13th, 2015 by IDAKA
 みなさん、お元気ですか?いよいよ2015年がスタートしました!! どんな年になるでしょうか?いやあ~、ワクワクしますね!
みなさん、お元気ですか?いよいよ2015年がスタートしました!! どんな年になるでしょうか?いやあ~、ワクワクしますね!
飽くまで現時点での己(オノレ)の観測ですが、国内は消費税の再増税が先送りとなり、今年は「じっくり議論を煮詰める年」。医薬品について政策的に大きな変動はないと考えます。ただ、製薬各社の研究開発、事業展開は海外シフトが一層進展し、相対的に日本市場のプレゼンスが下降する、という、ここ10数年来のトレンドは強まることはあっても弱まることはないでしょう。
さて昨年末の税制改正の取りまとめで懸案となっていた研究開発税制の見直し。当初浮上していた案は、製薬企業にとって、ものすごく不利でしたが、最終的には業界の意見がある程度、活かされる形で決着しました。それもこれも日薬連、製薬協の会長、理事長、厚労省の経済課長などが足繁く永田町を回った成果です。ただ、最終案について業界人の声を聞くと、意外にも評価は様々。どうも企業によって、影響に相当な違いがあるようです。
 研究開発税制は、企業の研究開発活動を後押しする目的で設定された一種の優遇措置です。いまは「法人税額の30%までなら、企業が投じた試験研究費のうち一定割合を税額から控除していいですよ」という形になっています。ところが15年度は全産業の法人税を下げるので、その分どこかで埋め合わせる必要がある。それで「研究開発税制の限度額を法人税額の30%から20%に下げましょう」という案が出ていたんです。
研究開発税制は、企業の研究開発活動を後押しする目的で設定された一種の優遇措置です。いまは「法人税額の30%までなら、企業が投じた試験研究費のうち一定割合を税額から控除していいですよ」という形になっています。ところが15年度は全産業の法人税を下げるので、その分どこかで埋め合わせる必要がある。それで「研究開発税制の限度額を法人税額の30%から20%に下げましょう」という案が出ていたんです。
これを聞いて製薬業界は騒然。幹部らが自民党の税調議員を何度も訪れて「イノベーションの促進というアベノミクスの基本政策に反する」と訴え、25%まで巻き返しました。さらに加えて「公的機関などとの共同研究に投じた費用は別枠で、5%まで控除していい」ということになりました。すなわち25%+5%=30%。いまと同率です。もちろん限度額の土台となる法人税そのものが下がるし、別枠で認められた共同研究費の控除には、様々な条件が付きますから、これまでと同じようには行きませんが、理論上は、うまくやれば恩恵が増える可能性もあります。当初案と比べれば、かなりいい線まで巻き返したように思うのですが。。。
7日の薬業四団体新年賀詞交歓会で、東京都医薬品工業協会の中山讓治会長が「主要な製薬企業では法人税の減税効果を打ち消し、いくつかの企業は増税になる。不十分だ」と“ダメ出し”しました。やはり企業間で影響にかなり格差があるようです。しかし、実際のところどうなのか?エビデンスもないので断言できません。2017年度には、さらに踏み込んだ税制の抜本改正が予定されているので、それまで状況をしっかり見極めていきたいと思います。
で、写真。一番目は7日、ザ・プリンスパークタワー東京で開かれた製薬業界最大の新年会、薬業四団体新年賀詞交歓会で撮影。右から武田薬品・長谷川閑史会長、アステラス製薬・野木森雅郁会長、第一三共・中山讓治社長。新年会ならではのスリーショット。各社の動きも注目です!!!そして2番目は12日に撮った、とある地域の成人式。みんな初々しい!日本はいま少子高齢化、社会保障改革、エネルギー問題、雇用対策、経済・外交等々、課題山積。それを乗り越えていくのは、君たち若者です。おっさんも、できることをしっかりやっていくよお~!と思わず胸の中で、叫び、強く誓った己(オノレ)でした。 それでは皆様、今年もどうかよろしくお願いいたします!!素晴らしい年になりますように!
Posted on 12月 29th, 2014 by IDAKA
 みなさんお元気ですか?今年も残すところ、あと3日。いかがお過ごしですか?
みなさんお元気ですか?今年も残すところ、あと3日。いかがお過ごしですか?
己(オノレ)は連日のように続く忘年会で、体重がかなり増えたような。。。。^_^; おそらく2015年は、一回り大きくなった己をお見せできることでしょう(体積的に。。。笑)1年間、薬新カフェにお付き合いいただき、ありがとうございました。また、来年もよろしくお願いいたします。
写真はNYブルックリンのバーでこの夏に撮影。カッコいいバーテンダーと、和やかに過ごすニューヨーカー達。。。次回の更新は15年1月13日です!よいお年を!
Posted on 12月 22nd, 2014 by IDAKA
 みなさんお元気ですか?
みなさんお元気ですか?
さて国内医薬品市場。後発医薬品シェアが急拡大しております。DPC(急性期入院定額払い)を採用している病院にも、後発品使用促進策を導入したことが予想以上に効いたようで、厚労省内に「一気に進み過ぎている」(城克文経済課長)と、懸念する声が出るくらいの勢いです。そのうえ、後発品企業間では「仁義なき値引き競争」が激化、保険薬価の90%引きなんてケースもあるそうで、ほとんど潰し合いですね。先発品メーカーも、そこに巻き込まれて「価格を下げざるを得ない」って泣いています。
で、これだけ後発品シェアが伸びて、その納入価格がどんどん下がっていると、心配されるのは、15年9月の薬価調査結果です。国内全医薬品の平均納入価が下がり、その平均納入価と、現在の保険薬価の乖離率が広がれば、当然、「保険薬価をもっとさげろ」という議論に直結します。消費税再増税の先送りで、ただでさえ厳しい社会保障費を、さらに引き締める方向になっています。
安倍政権は、すでに15年度から介護報酬を引き締めることを決めました。この決定は、ひどい!個人的には高所得高齢者の年金給付見直しが先だと思うのですが、しわ寄せは、いつも声が小さく、弱いところに行きます。それはともかく、こんな状況ですから、保険薬価も、できるだけ低く抑えようということになるでしょう。後発品の保険薬価は、高、中、低と3段階ありますが、少なくても、次回の薬価改定で、高、中は廃止されるんじゃないでしょうか?
で、写真は小田急線内の車内広告。ようやっとやってくれました。電車内で、ヘッドホンから音漏れしているチャン兄、チャン姉、結構いますよね。彼らには、声を掛けても、聞こえないからやっかいです。己(オノレ)は肩たたいて「ちょっとボリューム下げて」ってお願いします。大体、「あ、了解」って感じで下げてくれるんですが、たまに、こっちをじっと見つめ返すだけという気持ち悪い子に遭遇したりします。なんで、この広告はうれしい。しかも、 花くまゆうさく さんのイラストです。どこまで効果があるかわかりませんが、やらないよりましですね。ではみなさま今年も残すところあと10日、素敵な毎日をお過ごしください。
Posted on 12月 15th, 2014 by IDAKA
 みなさんお元気ですか?衆院選は大方の予想通り自民、公明与党の勝利に終わりました。自民が291議席で4議席減らしましたが、単独過半数超(定数475議席)を維持。一方の公明党が35議席で、4議席増やしたので、自公与党の勢力は公示前と変わらず326議席です。もっとも1票格差是正のため、今回は定数を公示前(480議席)より5議席削ったので、与党の勢力は「維持」というより、むしろ「強化」されたと言った方がいいかも知れません。 日本は議会制民主主義ですから、確かに、選挙に勝った党が「国民の信任を得た」と言って間違いないんですが、選挙民は、何もいまの与党がやっている政策すべてに賛成し、全幅の信頼感を以て丸投げした訳ではない。投票率も約50%で戦後最低だ。しかし、選挙後、安倍総理や、麻生財務相らの発言を聞くと、「約2年の政権運営、経済政策(アベノミクス)が支持された」と言って憚らないので、己(オノレ)は一抹の不安を感じています。別に、すべての国民が自民党の政策すべてにOKしたわけじゃないですから! しっかし、投票において、候補者名と、政党名を書くだけなんてナンセンスじゃないでしょうか?せめて候補者、政党には個別政策を5つくらいあげてもらい、「〇」「×」を書くくらい、有権者に、意思表示させてくれてもいいのではないでしょうか? どうあれ、安倍政権は何もなけりゃ後4年は安泰です。24日に予定する第3次の組閣もほとんど第2次の布陣のままで行くようです。しかし、15年度の予算編成は1月初旬までかかりそうな気配です。第1(金融政策)、第2(財政出動)の矢は、もう散々やったんだから、いいよ。いよいよ第3の矢。企業や個人の「成長戦略」をどうするのか?そこが問われます。実のところ、安倍政権は、製薬産業をどう見ているのか?日本の基幹産業として育てる気があるのか?ないのか?まずは15年度の税制大綱に、業界が要望している「研究開発税制の控除額延長」が通るかどうかが焦点になりましょう。
みなさんお元気ですか?衆院選は大方の予想通り自民、公明与党の勝利に終わりました。自民が291議席で4議席減らしましたが、単独過半数超(定数475議席)を維持。一方の公明党が35議席で、4議席増やしたので、自公与党の勢力は公示前と変わらず326議席です。もっとも1票格差是正のため、今回は定数を公示前(480議席)より5議席削ったので、与党の勢力は「維持」というより、むしろ「強化」されたと言った方がいいかも知れません。 日本は議会制民主主義ですから、確かに、選挙に勝った党が「国民の信任を得た」と言って間違いないんですが、選挙民は、何もいまの与党がやっている政策すべてに賛成し、全幅の信頼感を以て丸投げした訳ではない。投票率も約50%で戦後最低だ。しかし、選挙後、安倍総理や、麻生財務相らの発言を聞くと、「約2年の政権運営、経済政策(アベノミクス)が支持された」と言って憚らないので、己(オノレ)は一抹の不安を感じています。別に、すべての国民が自民党の政策すべてにOKしたわけじゃないですから! しっかし、投票において、候補者名と、政党名を書くだけなんてナンセンスじゃないでしょうか?せめて候補者、政党には個別政策を5つくらいあげてもらい、「〇」「×」を書くくらい、有権者に、意思表示させてくれてもいいのではないでしょうか? どうあれ、安倍政権は何もなけりゃ後4年は安泰です。24日に予定する第3次の組閣もほとんど第2次の布陣のままで行くようです。しかし、15年度の予算編成は1月初旬までかかりそうな気配です。第1(金融政策)、第2(財政出動)の矢は、もう散々やったんだから、いいよ。いよいよ第3の矢。企業や個人の「成長戦略」をどうするのか?そこが問われます。実のところ、安倍政権は、製薬産業をどう見ているのか?日本の基幹産業として育てる気があるのか?ないのか?まずは15年度の税制大綱に、業界が要望している「研究開発税制の控除額延長」が通るかどうかが焦点になりましょう。
で、写真は最寄駅で撮影。かなたに富士山。観えますか?「晴れてよし 曇りてもよし 富士の山」。それではみなさま、素敵な一週間をお過ごしください!
Posted on 12月 8th, 2014 by IDAKA
 大塚製薬が米国のバイオベンチャー、アルバニア社を約4200億円で買収することになりました。中枢神経系(CNS)領域を強化するのが狙いです。こういう場合、金銭授がどうなるのか。不勉強でよくわかりませんが、円安が急速に進行している中、かりに円建てで考えると、必ずしもいい時期とは言えない気がします。どうなんでしょうか?大塚製薬を束ねる大塚ホールディングスの樋口達夫社長兼CEOに記者会見で尋ねると、概ね以下のように返答しました。「為替がどうあれ、買う時は買う。かつてフランスの会社を買収する時、円安でどうしようかと思ったが、結果、買収し、いまや大きな収益を上げている」。頼もしい限りです。間違いなく年末の明るい話題のひとつです。 ただ、己(オノレ)が気になるのは、アルバニアが持っている情動調整障害(PBA)治療薬ニューデクスタ。11年2月に米国で発売され、100億円超の売り上げになっているそうです。PBAという適応症を取得しているのは、世界でニューデクスタだけ。大塚の買収を後押しした要因のひとつです。パーキンソン、脳卒中、アルツハイマー型痴ほう症の患者で、突然泣いたり、笑ったり症状を指すそうです。で、何が気になるかというと、意外に投与基準が難しいのではないかと思うのです。「製薬企業は無理やり新たな疾患を作り出している!!」という、今流行りの製薬企業謀略説を当て嵌める気はサラサラありませんが、本当に感情が昂って泣いているのか?何か中枢に異常があって泣いているのか?線引きしにくい。曖昧なままにすると、安易な投与が進み、本来の薬が持つ意義を潰しかねない。そう思うのです。日本での開発販売計画は「まだ何も決まっていない」ということですが、上市の際は、是非、しっかりした投与基準を策定して欲しいものです。
大塚製薬が米国のバイオベンチャー、アルバニア社を約4200億円で買収することになりました。中枢神経系(CNS)領域を強化するのが狙いです。こういう場合、金銭授がどうなるのか。不勉強でよくわかりませんが、円安が急速に進行している中、かりに円建てで考えると、必ずしもいい時期とは言えない気がします。どうなんでしょうか?大塚製薬を束ねる大塚ホールディングスの樋口達夫社長兼CEOに記者会見で尋ねると、概ね以下のように返答しました。「為替がどうあれ、買う時は買う。かつてフランスの会社を買収する時、円安でどうしようかと思ったが、結果、買収し、いまや大きな収益を上げている」。頼もしい限りです。間違いなく年末の明るい話題のひとつです。 ただ、己(オノレ)が気になるのは、アルバニアが持っている情動調整障害(PBA)治療薬ニューデクスタ。11年2月に米国で発売され、100億円超の売り上げになっているそうです。PBAという適応症を取得しているのは、世界でニューデクスタだけ。大塚の買収を後押しした要因のひとつです。パーキンソン、脳卒中、アルツハイマー型痴ほう症の患者で、突然泣いたり、笑ったり症状を指すそうです。で、何が気になるかというと、意外に投与基準が難しいのではないかと思うのです。「製薬企業は無理やり新たな疾患を作り出している!!」という、今流行りの製薬企業謀略説を当て嵌める気はサラサラありませんが、本当に感情が昂って泣いているのか?何か中枢に異常があって泣いているのか?線引きしにくい。曖昧なままにすると、安易な投与が進み、本来の薬が持つ意義を潰しかねない。そう思うのです。日本での開発販売計画は「まだ何も決まっていない」ということですが、上市の際は、是非、しっかりした投与基準を策定して欲しいものです。
で、写真は谷中の朝倉彫塑館で撮影。屋上庭園の西側にある作品です。作品名がわからないのですが、「夕陽を見つめながら明日の躍動を誓う」って感じで、力が湧いてきます。あと、これを見ていたら、いつの間にか、デビルマンのエンディングテーマを口ずさんでいました。「だあれも知らない 知られちゃいけぇ~ないー♪」って歌(これがわかる人は同世代、(*^_^*))。それでは皆様、寒さに負けず、素敵な一週間をお過ごしください。
Posted on 12月 1st, 2014 by IDAKA
![securedownload[1]](http://www.yakushin-iryou.co.jp/wp-content/uploads/securedownload1-300x225.jpg) みなさんお元気ですか?さんむいですねえ~。 さて、いよいよ衆院総選挙。明日2日(火)公示、そして14日(日)投票です。
みなさんお元気ですか?さんむいですねえ~。 さて、いよいよ衆院総選挙。明日2日(火)公示、そして14日(日)投票です。
今週、来週は本格的な選挙戦に突入します。前回、己(オノレ)も書きましたが、今回の解散総選挙は「大義がない」という意見が多いです。なぜなら消費税増税の先延ばしは、もともと自民党でなく、野党が強く言っていたことだからです。与野党「オール賛成」だから、消費税の先送りは争点にはならないのです。己は、はじめ、そこに違和感を抱き、前回、このブログで「やる必要無し」っていいました。ただ、先週、先々週と、色々な御仁と、このことについて話したり(その多くは居酒屋談義ですが、笑)、識者の意見を読んだり聴いたりしているうちに、「ああ、安倍政権にとっては大義がなくてもやらざるを得なかったんだなあ。ある意味追い込まれたんだなあ」と思うようになりました。
消費増税を先送りするには来年の通常国会に「先送り法案」を出さねばならない。もし解散総選挙無しで国会論議に突入すれば野党から「いまさら宗旨替えするのはおかしい!」「アベノミクスは失敗だ!」と、ねちっこくかつ厳しい追求を受けたでしょう。財務省も、色んな手を使って妨害工作をしたかもしれません。しかし、解散総選挙で、再度、国民の信託を得れば「国民が我々政権の選択を支持したんだよ。なんか文句あっか?」って、押し返すことができるわけです。自民党は多少議席を減らすかもしれないけれど。。。。
それから、もしかしたら選挙中、ビッグサプライズもあるかもしれません。
来週8日に発表される7―9月のGDP2次速報値。先に発表された1次速報は年率マイナス1.6%でしたが、マイナス幅が0%台半ば~1%程度に縮小する可能性が高いと言われています。選挙戦真っ最中ですよ。自民党は「ほら見てください!アベノミクスは、やはり失敗していないんです!!」って強く訴えるでしょう!!そうなれば意外に議席は減らないかもしれません。
で、写真は新宿西口で撮影。ラーメンとおでんの屋台。昭和の香り。なんか風情が有って、いい感じでしょう?では皆様、素敵な一週間をお過ごし下さい!
Posted on 11月 25th, 2014 by IDAKA
 みなさんお元気ですかあ?
みなさんお元気ですかあ?
3連休いかがお過ごしでしたか?
11月24日(月)の更新はお休み。
次回、更新は12月1日(月)です。
商店街はどこもジングルベル!
いやでも年の瀬を感じさせますね。
楽しく充実した一週間をお過ごし下さい。
Posted on 11月 17th, 2014 by IDAKA
 安倍政権は15年秋に予定していた消費税再増税を先送りし、衆院解散・総選挙に踏み切ることを決めました。安倍総理が外遊中に、アチコチのメディアが見通し記事を載せていたから、いまさら驚くこともないですね。己(オノレ)の知る限りでは、11月6日(木)発売の週刊文春11月13日号が「12.14総選挙、緊急予測」という特集記事を載せたのが最初。「おお、勇気あんなあ~」と関心していたら、翌週、一般各紙が次々に取り上げ、すでに11日(火)の段階で「2日公示14日投票」という具体的な日程まで報ぜられました。また、10日(月)に発売された文藝春秋には、内閣参与で長く総理のブレーンを務めている浜田宏一・米エール大学名誉教授と、本田悦朗静岡大学教授が「アベノミクスはこのままでは崩壊する」という見出しの対談で「消費税の増税先送りすべき」と強く主張しています。増税先送りと解散総選挙について、安倍総理は、先週まで「私自身が口にしたことは一度もない」と話していました。だから、初めのうちは「安倍政権は、ガバナンスがなっていない。情報がボロボロ漏れちゃっているじゃないかあ~」と思っていました。しっかし、こんだけ沢山、情報が漏れてれば、誰だっておかしいと思いますよね。途中から「ああ、これは世論の反応を測り、次の一手に向けて環境整備しているんだな」と思い直しました。なんか、愚弄されているような気がして、嫌な感じです。
安倍政権は15年秋に予定していた消費税再増税を先送りし、衆院解散・総選挙に踏み切ることを決めました。安倍総理が外遊中に、アチコチのメディアが見通し記事を載せていたから、いまさら驚くこともないですね。己(オノレ)の知る限りでは、11月6日(木)発売の週刊文春11月13日号が「12.14総選挙、緊急予測」という特集記事を載せたのが最初。「おお、勇気あんなあ~」と関心していたら、翌週、一般各紙が次々に取り上げ、すでに11日(火)の段階で「2日公示14日投票」という具体的な日程まで報ぜられました。また、10日(月)に発売された文藝春秋には、内閣参与で長く総理のブレーンを務めている浜田宏一・米エール大学名誉教授と、本田悦朗静岡大学教授が「アベノミクスはこのままでは崩壊する」という見出しの対談で「消費税の増税先送りすべき」と強く主張しています。増税先送りと解散総選挙について、安倍総理は、先週まで「私自身が口にしたことは一度もない」と話していました。だから、初めのうちは「安倍政権は、ガバナンスがなっていない。情報がボロボロ漏れちゃっているじゃないかあ~」と思っていました。しっかし、こんだけ沢山、情報が漏れてれば、誰だっておかしいと思いますよね。途中から「ああ、これは世論の反応を測り、次の一手に向けて環境整備しているんだな」と思い直しました。なんか、愚弄されているような気がして、嫌な感じです。
消費税の再増税は本日17日公表の7-9月のGDP速報値などを参考に判断すると言っていたのに、もうかなり前に先送りを決めていたものと思われます。それに本来、消費税増税と、解散総選挙はまったく別のものだと思うんですが、どうでしょうか?今度の選挙は「アベノミクスの信を問う」というのが、大義名分だそうですが、そもそも15年10月に再増税するというのがアベノミクスなんだから、その基本路線を変更して「信を問う」はないでしょう。国民の7割は増税に反対、野党もみんな反対なんだから、わざわざ選挙で「消費税増税を先送りをしたのは正しい選択でしたか?先送りしちゃった私、嫌いですか?」と問う必要は全くないんです。「先送りするつもりはないけど、どうですか?」と問うならわかるけど。。。この忙しい年の瀬に、選挙なんて迷惑この上ない。やんなくていいです。しかし、今なら自民党が勝つでしょう。安倍総理は、この期に、自民・公明の議席数を増やし、圧倒的な勢力を固めたいのでしょう。その先にある狙いは何か?長期政権の確立、そして念願の憲法改正。そういう青写真が薄らと見えています。己が命名するなら「迷惑解散」「わがまま解散」ってとこでしょうか。
製薬業界はとりあえず、15年10月の薬価改定を免れたのですが、いかんせん社会保障に充てる消費税の増税が先送りされたわけで、財務省は「お金ないんだから、製薬業界も協力してね」と言うでしょうね。次の薬価改定は16年4月になり、議論の時間はできました。厳しい提案が出てきそうです。また、消費税増税が1年半先送りということになると、17年4月です。となると、16年4月(定例改定)、17年4月(増税改定)、18年4月(定例改定)と、3年連続改定となり、毎年改定論議に弾みをつけることになるかもしれません。
写真は新宿西口をビルの8階エントランスから撮影。ミニチュアみたいでちょっと、きれいでしょ?では皆様、本格的な冬の足音がが迫ってきました。お体に気をつけて。素敵な一週間をお過ごし下さい!ヾ(*´∀`*)ノ
Posted on 11月 10th, 2014 by IDAKA

武田・長谷川会長とウェバー社長
みなさん、お元気ですか?永田町は、またしても「政治とカネ」を巡る問題で大わらわ。消費税再増税を予定通り15年10月に実施するかしないかで、難しい判断を迫られる時期だけに、安倍政権は、さぞ頭が痛いでしょう。来週17日に、7ー9月の経済成長率(GDP)の速報値が発表されると再増税がどうなるか。我々国民にも、かなり鮮明に見えてくるでしょう。まあ、国内は、いつだって課題山積ですから。。しっかりして欲しいのは外交ですよ。連日、何百隻も日本の領海に押し寄せ、違法なサンゴ漁を繰り返している中国漁船。これはもうどう見ても海賊行為でしょう。早くなんとかして欲しい。海上保安庁の巡視船では、対応が間に合わないと聞きます。安倍総理は、集団的自衛権の発動解釈を強引に緩め、自衛隊を発動しやすくし

第一三共・中山社長
たんだから、いまこそ自衛隊を援護派遣すべきです。それとも米国の要請がないと、派遣できないとでもいうんでしょうか。さすがにこの件で、米国が派遣要請することはないです。日本の問題ですからね。誰にも頼らず、自らの判断で決めなきゃヾ(*´∀`*)ノ
さて、先週、先々週と、製薬企業各社の14年4-9月期間決算(中間)の発表がありました。己(オノレ)も、可能な限り記者会見に足を運びました。
武田薬品工業は今年10月、株式時価総額で、アステラス製薬に抜かれてしまいました。1か月たったいまも、アステラス、トップで推移しているようです。記者会見で、それについて問われると、クリストフ・ウェバー社長は「私は競争志向の人間なんで、アステラスの後ろにいる現状は満足できない」と強調、トップ奪還に意欲を見せました。実際、武田の課題は、徐々に改善されていますし、時価総額の差も、アステラス約4兆円に対し、武田約3兆9000億円で、それほど大きくないので、まだまだ返り咲きは可能でしょう。アステラスが、この期にどこまで成長して、武田を、ぶっちぎりで引き離すかが、カギです。
一方、かつて、売上高が武田に続いて第2位だった第一三共は、いまや毎年、3位以下が定位置になっています。12月に早期退職者優遇の特別措置を使ってリストラを予定しているほか、インド・ランバクシー社の実質的な譲渡およびマネージメントからの撤退も着々と進めています。いまは拡大路線より、引き締め路線です。売上高ランキングも、さらに下がるかもしれません。中山讓治社長は「(ランバクシーが連結から外れて)売上が減るのは残念だが、内実的に強い会社にしたい」と発言、社員ひとりひとりには「自分の役割だけ果たしていれば、後はどっかの調整役がやってくれる、という意識が間接部門を増やしてきた。役所的な会社ではなく、自分がオーナーだという気持ちを持って、人任せしないことが大事」と述べました。この先の戦略に注目します。
と振り返ると、国内製薬業界にも地殻変動が迫ってきているように感じます。
ではみなさん、きょうは、すっごいいい天気ですね!!充実した楽しい素敵な一週間をお過ごし下さい。
Posted on 11月 4th, 2014 by IDAKA
みなさんお元気ですかあ?3連休いかがお過ごしでしたか?お天気には恵まれませんでしたが、まあ、モノは考えよう&物は言いようと、申しますヽ(*´∀`)ノのんびり過ごすには、かえって良かったかもしれませんね。
11月3日(月)の更新はお休みいたします。次回、更新は10日(月)になります。
楽しく充実した一週間をお過ごし下さい。
 みなさん、お元気ですか?いよいよ2015年がスタートしました!! どんな年になるでしょうか?いやあ~、ワクワクしますね!
みなさん、お元気ですか?いよいよ2015年がスタートしました!! どんな年になるでしょうか?いやあ~、ワクワクしますね!  研究開発税制は、企業の研究開発活動を後押しする目的で設定された一種の優遇措置です。いまは「法人税額の30%までなら、企業が投じた試験研究費のうち一定割合を税額から控除していいですよ」という形になっています。ところが15年度は全産業の法人税を下げるので、その分どこかで埋め合わせる必要がある。それで「研究開発税制の限度額を法人税額の30%から20%に下げましょう」という案が出ていたんです。
研究開発税制は、企業の研究開発活動を後押しする目的で設定された一種の優遇措置です。いまは「法人税額の30%までなら、企業が投じた試験研究費のうち一定割合を税額から控除していいですよ」という形になっています。ところが15年度は全産業の法人税を下げるので、その分どこかで埋め合わせる必要がある。それで「研究開発税制の限度額を法人税額の30%から20%に下げましょう」という案が出ていたんです。








![securedownload[1]](http://www.yakushin-iryou.co.jp/wp-content/uploads/securedownload1-300x225.jpg)