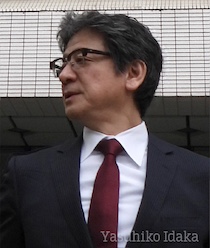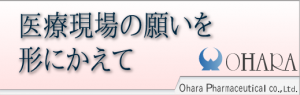Posted on 5月 25th, 2020 by IDAKA
 みなさん、お元気ですか?
みなさん、お元気ですか?
新型コロナ感染症拡大に伴う緊急事態宣言が間もなく東京でも解除されます。予定していた5月末より数日早い!!!
何はともあれ、うれしいですね。
いわゆる「自粛」。いやあ堪えましたねえ~。
この期間、みなヒステリックになり、通常ではありえないバカバカしい出来事や、歪んだ出来事が多発したように思います。
おそらく秋以降、第2波、第3波が来るのでしょうから、政府はしばらく引き締めたり、緩めたりの政策を繰り返すでしょう。
今回、緊急事態宣言が解除されたからと言って、パーっと騒ぐわけにもいかない。
まあ、おっかなびっくり解き放たれましょう!!!
しかし、新型コロナ禍の前後で、以前のままのもの、大きく変わらざるを得ないものがある。
逆を言えば、以前のままであってはいけないもの、大きく変えてはならないものもある。
今を生きる私たちには、それをしっかり見極めて明るい未来を創る責任があるのではないでしょうか。そんな風に思っています。
写真は近くのカフェ。散歩中に発見、テラス席があっていい感じ。ハワイアンミュージックが流れててかなり無理すれば気分はアロハ~!!!
それでは皆様、素敵な1週間をお過ごしください。
Posted on 5月 18th, 2020 by IDAKA
 みなさん、お元気ですか?
みなさん、お元気ですか?
めっきり移動の機会が減って、メタボ化が心配な今日この頃です。
さて製薬企業各社の決算発表がピークを迎えております。説明会は時節柄、すべてリモートですが、先週13日水曜日は武田薬品、大日本住友、エーザイ、三菱ケミカルHDの発表が集中しました。しかも武田薬品とエーザイ、大日本住友と三菱ケミカルHDは時間もかぶっていて大変悩ましい状況でした。リアルな説明会だったら、場所も違い、それなりに移動に時間がかかるので、きっぱり絞り込むんですが、リモートだと、PCとスマフォさえあれば、時間が重複してもなんとかアクセスだけはできちゃうんですよね。
で、今回4件ともアクセスし、音源はしっかり確保できました。しっかし、この疲労感と言ったらない。集中力も弱まるし。。。。よくよく考えれば、後ほどHPで音源を公開してくれる。質問はできないけど。ということで、今後はリモートでも欲張らないで絞り込みしよう!!!と誓うのでした。(とはいえ13日の4社はすべて絞り込めないくらい、リアルに聞きたかったんで仕方がなかったのです)。
写真はゴールデンウィーク中の上野公園。整然としておりました。。。それではみなさん、素敵な一週間をお過ごしください。
※大日本住友製薬が6月に国内販売する統合失調症治療薬ラツーダについて記事を書きました。是非ともご覧ください。
Posted on 5月 11th, 2020 by IDAKA
 みなさん、お元気ですか?
みなさん、お元気ですか?
厳しい外出自粛要請下でのゴールデンウィーク。どう過ごされましたか?
連休は明けましたが、記者会見も取材も打ち合わせも懇談もリモート、リモート、リモート、リモートです。
ここでも何度か触れましたが、ネット環境さえ整っていれば、すぐにやり取りでき、移動の手間も省けるなど確かにいい面ある。
しっかしなんか今一つ物足りないんですなあ~これが。
言語以外の表情、態度、服装、声色など、いわゆるノンバーバルコミュニケーション(非言語相互交流)の発信力が非常に弱いんですね。リモートって。。。
こんな状態が続いたら、人と人の交流において、「身体」は生殖の時以外、ほとんどいらなくなりますね。いや、それすら危ういか。。。。。
これを良しとしたら、人の交流は脳みそを直接ネットでつなげばこと足りちゃうわけです。
昭和の暑苦しくギュウギュウの、それこそ今でいう三密(密閉、密集、密接)が当たり前の日常を何10年も過ごしてきた私には、やはり何か違和感があります。
ああ、いかんいかん、いかんぞお、また愚痴ぽくなっている。
放っておくとネガティブな思考に陥りがちな今日この頃。
「身体」を整えて、免疫力を高めましょう!!!!!
それではみなさん、素敵な一週間をお過ごしください!!!
Posted on 4月 27th, 2020 by IDAKA
 みなさん、お元気ですか?緊急事態宣言後、3週間目を迎えます。
みなさん、お元気ですか?緊急事態宣言後、3週間目を迎えます。
先日、あるテレビ番組で感染症の専門家が「パンデミックが世の中の技術や政策の進行を10年くらい早めることはままある」と話していました。まさにその通りですね。3月2日付けでこのブログにアップした私の予測も今のところ大きな外れはない。⇒【新型コロナウイルスが社会に「壮大なる実験」をもたらしていますね】https://www.yakushin-iryou.co.jp/?p=8005
ただ、世の進展も、いい面、悪い面あります。
いま緊急事態のどさくさで、テレビ局などが人の動きを衛星で把握したりしています。また、生活補償の関連でマイナンバーの活用を強化すべきとか、ビッグデータを用いて地域ごとに感染者の多寡を把握すべきという声も大きくなっています。当座の感染対策を考えると効果はありましょうが、新型コロナ禍後のことを考えると、そう易々と、賛成できません。むしろ、怖いです。国家の管理、監視が強まり、自由を失うくらいなら、いつ新型コロナに感染するかわからないロシアンルーレットのような状況下で、びくびく暮らしながら、ただただパンデミックが過ぎ去るのを待つ方が百倍まし、と私は思います。
新型コロナ禍で、世の中は急速に変化します。その「変化」が人々をより幸せにする、素晴らしい「進化」となればいいなあと願ってやみません。
それではみなさん、まだまだ巣籠もり時間が続きますが、なんとか工夫して楽しく。。。。。素敵な一週間をお過ごしください。
Posted on 4月 20th, 2020 by IDAKA
 みなさん、お元気ですか?緊急事態宣言が出て、ちょうど2週間経ちました。5月6日まで残すところ、あと2週間ちょっとです。
みなさん、お元気ですか?緊急事態宣言が出て、ちょうど2週間経ちました。5月6日まで残すところ、あと2週間ちょっとです。
いま私たちは「新型コロナ感染を“拡大”から“減少”に転ずるには、人と人の接触を8割減らす必要がある」という仮説に基づく壮大な実証研究に参加しております。
しっかし、「8割減」を1か月続けるってきつい。私なんて緊急事態宣言が始まる前から、ほとんど部屋にこもっていますので、そっからさらに8割削減したら、存在自体が溶けてなっちゃいますよお(泣笑)。そんな冗談はともかく、まあ、なんとかみんなで努力し、5月6日までに明るい光が見えることを期待しています。
そろそろ緊急事態宣言が出た4月7日後に感染した方たちの数値が上がって来るころで、毎日の感染確認数の推移を期待をもって見つめています。もっともPCR検査が以前より若干受けやすくなっているので、7日より前に感染した方がまだまだ出てくることを考えると、“減少”に転ずるのは「もっと先」という厳しい見方もあります。緊急事態宣言が第2次、第3次と延長されないように祈るばかりです。
公園の木々は何事もなく青く風に揺られ、空も何事もなく澄み切っています。人の世のはかなさを実感する今日この頃です。
それではみなさん、素敵な一週間をお過ごしください。
MeijiSeikaファルマの今を記事にしました。どうぞご覧ください。
Posted on 4月 13th, 2020 by IDAKA
 みなさん、お元気ですか?今週は、そぼ降る雨でスタート。全国7都府県で、新型コロナウイルス感染拡大の緊急事態宣言が出て、「巣籠もり」度合いが一層、高くなっていることと思います。とりあえず5月6日まで。耐えましょう!!
みなさん、お元気ですか?今週は、そぼ降る雨でスタート。全国7都府県で、新型コロナウイルス感染拡大の緊急事態宣言が出て、「巣籠もり」度合いが一層、高くなっていることと思います。とりあえず5月6日まで。耐えましょう!!
前回も触れましたが、あちこち、色んな情報が飛び交って、世の中全体が混乱気味です。商売柄、時間さえあればテレビを含む各種メディアが発信する関連情報をチェックしていますが、混乱は増幅するばかりです。とくにテレビ番組は、みんな感情的で、ムキになって発言していて、危ないなと思います。なんでそんなに怒っているんでしょう?怒ったってしょうがないのに。。。
いま個々人が自らの行動を抑制し、感染拡大のピークをなだらかにするのは、とても大事なことで、私たち国民に自粛を求めるのは当たり前だとしても、悪戯に危機感を煽ればいいってもんじゃないんじゃないでしょうか?
データをわかりやすく示して、静かに説明すれば、多くの国民は自分の頭で考え、納得したうえで、しっかり自粛できると思います。何も若者をしかりつけたり、恫喝したりする必要はない。
何しろデータの扱いがおおざっぱで、かつ説明が乱暴なので、いまどんな状態にあるのか、私たちが客観的に把握するのは至難の業です。例えば日々、各国ごと、都道府県ごとの感染者数が発表されますが、対人口比はほとんど示されません。また、この感染者数にしても、発症まで1~14日という潜伏期間、医療機関に行くまでの迷っている期間、PCR検査を実施してもらうまでの期間、結果が出るまでの期間を含めると、感染したのは平均して想定10日程度前。だから数値として出ているのは「今現在感染した人」ではない。そういうことさえ、忘れられがちです。
これだけ自粛しているんだから「まだ駄目だ。甘い」と締め付けるばかりでなく、何か「成果らしきもの」、あるいは「成果の兆しらしきもの」を示すデータが見たい。感染者でいえば、単純に人数を公表するだけでなく、対人口比、重度、軽度、無症状者別、改善退院者数も合わせて公表すべきです。世の中、全体が新型コロナによる自粛で、ストレス一杯です。このままだと新型コロナ感染以外の疾患も増加するでしょう。
為政者は「ポジティブなデータを開示すると、民衆は自粛を緩めてしまう」と考えているようですが、私たちをあまり見くびらないで欲しいものです。新型コロナウイルスに関する恐怖感の植え込みははもう十分、いきわたりました。ネガティブなデータと併せて、ポジティブなデータが開示されるからこそ、私たちは自粛の意義を感じ、「さらにがんばろう」という気持ちになれるのではないでしょうか。
写真は近所の道路で。色とりどりのチョークで描いた子供の落書き。最近は珍しい。きっとノリノリで描いたことでしょう。夢があって素晴らしい!!!ほっこりしました。それでは皆様、素敵な一週間をお過ごしください。
Posted on 4月 6th, 2020 by IDAKA
 みなさんお元気ですかあ?
みなさんお元気ですかあ?
世界中、新型コロナで大変なことになっています。で、思うんですけど感染爆発より先にメディアやSNSが放つ関連情報が、もうすでにオーバーシュート(爆発的拡大)です。
専門家とか、第1人者とかバンバン出てきて、それぞれ全く違う意見を述べて否定しあったりします。メディアもSNSもことさら、危機感、不安感を煽りまくって、もうヒステリック極まりない。そこに虚実ないまぜのフェイクニュースを流す不届き者の輩が、事態の深刻さを全く認識せず(できず)にキャッキャッはしゃいで跳ね回っていたり。。。やばい状態です(苦笑)
情報を巡る色んな歪み、問題が噴出しています。だから今こそ、私たち1人1人が自分で精査し、考え、判断することが大事。しっかり訓練いたしましょう!!!
私はいまからこれ【写真】を食します!!!!目下、私のスローガンは
「戒厳令下で目指せ!!!健やかブロイラー生活!!!」
それではみなさん、素敵な一週間をお過ごしください。
医薬経済4月1日号に記事を書きました。よかったらご覧ください。
Posted on 3月 30th, 2020 by IDAKA
 はい、みなさんお元気ですかあ?いやあ、在宅勤務(テレワーク)もかれこれ、2か月近くになりますね。3月上旬から下旬にかけて製薬はじめヘルスケア関連企業のみなさんに色々、お話をお聞きしました。テレワークを実施していないところはほとんどないですね。
はい、みなさんお元気ですかあ?いやあ、在宅勤務(テレワーク)もかれこれ、2か月近くになりますね。3月上旬から下旬にかけて製薬はじめヘルスケア関連企業のみなさんに色々、お話をお聞きしました。テレワークを実施していないところはほとんどないですね。
「もう慣れちゃった。平時に戻っても会社行くのめんどくさい」。なんて声も聞こえてきました。別にいいですよね。それでも。ただ、システム構築にはまだまだ不備があるようです。例えば、全面的に在宅勤務に切り替えている、とある大手製薬企業。会社には本人に直接つながる回線が1人ずつあって、電話もすべてダイヤルインです。でも先ごろ、電話したら留守電。時間空けて再度、チャレンジして留守電。またかけても留守電。ええ加減、隣の人取ってくれや!!!誰もいないんかい(怒笑)。で、メールしてようやく先方から電話をいただけました。在宅勤務だと会社の留守電を聞くことはできないそうなんです。今回のアクセスは大分、遠回りになり、時間がかかりました。なんか簡単なことのようで、見過ごされているとこみたい。とささいなことですが、テレワークの本格実施、恒久化(新薬加算みたい、笑)には、細かな課題もありそうです。
写真は夕暮れの国会議事堂。日は沈みまた日は昇る。
ということでみまさま、素敵な一週間をお過ごしください。
Posted on 3月 23rd, 2020 by IDAKA
 みなさん、お元気ですか?
みなさん、お元気ですか?
電車の中や街中で、コホンと咳をする人がいるとピクッと反応する自分。逆に自分がウウンッと咳払いをひとつすると何となく周囲の冷たい空気を感じてしまう今日この頃です。なんだか、いやあ~な世の中になりました。一時的であることを願うばかりです。。
「我々は見えない敵と闘っている」(トランプ米大統領)、「第二次世界大戦後、最大の試練」(メルケル独首相)、「我々は戦争状態にある」(マクロン仏大統領)。新型コロナウイルスに対して、各国首脳陣が次々に、おどろおどろしいメッセージを発信しています。しかし、最近読んだ何冊かの書籍によると、人類がウイルスの封じ込めに成功した例は天然痘ウイルスだけ。その他、多くの新型ウイルスは、各種、対策を講じているうちに、我々ヒトに耐性ができて「共存」していく。そんなオチを迎えるのが定番のようです。新型コロナは感染拡大を続けており、いま、世の中全体が自粛ムードになるのは仕方ないにせよ、どっかの段階で闘わずに「共存」する。個々人はできる範囲の対策をしながら、開き直る。そんな発想も必要になんじゃないかと思います。みなさん、とにかく免疫力を高めましょう!!!!
写真は春を象徴する桜。それではみなさん、素敵な一週間をお過ごしください。
Posted on 3月 16th, 2020 by IDAKA
 みなさん、お元気ですか?
みなさん、お元気ですか?
新型コロナウイルス、COVID-19の感染拡大で世の中、騒然としております。というかほとんど事態に進展はなく、このブログの書き出しも1か月ばかり変わり映えしない。
先週3月11日、東日本大震災から9年が経過しました。しかし、新型コロナの影響で、なんだかいつもよりスポットが弱まっているように感じました。東日本大震災では東京電力の福島第一原発の事故で、放射能汚染が問題となり、世界中を恐怖に陥れました。この問題は、まだ完全に解決しておらず、被災者を苦しめているのに、時の経過とともに私たちの記憶は薄れ、日々の暮らしに埋没してきました。
新型コロナはどうでしょうか?おそらくウイルを撲滅することはできないから、ワクチンや治療薬ができるまで私たちは免疫力を高めることしかできない。そんなこんなで、意外に長い時間が経過していくのではないでしょうか?マスメディアは各国、各県、各組織ごとに、感染者、死亡者を随時公表していますが、それに一体、どのくらいの意味があるのか。個人的には、いたずらに恐怖心をあおるだけなんじゃないかと思います。というのは感染者数はすでに公表の何倍もに広がっていて、いまはもう、いかに防御するかより、むしろ自分がかっかたら、家族がかかったら、同僚、友達がかかったらどうするか。そういうことを考える段階だと思うからです。
感染力とか、発症率とか、もっというと遺伝子多型の違いでの差とか、そういったデータが出てきてほしいもんです。「目に見えない」「匂わない」「知らぬ間に体内に入り込む」という点で、新型コロナと放射能には共通点があります。だからこそ、私たちは委縮してしまうのですが、ずっと委縮しているわけにもいかないですよね。科学的な研究データの蓄積を待って、それに基づき冷静に毎日を過ごしましょう!!!!
写真は久々に訪れたスターバックス。カップに桜の絵が。そういえば春なんですねえ。それではみなさん、素敵な一週間をお過ごしください。
 みなさん、お元気ですか?
みなさん、お元気ですか?