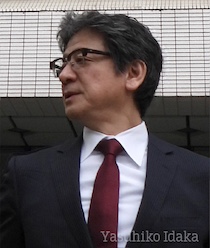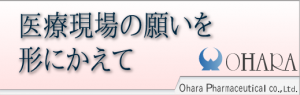Posted on 9月 4th, 2024 by IDAKA

◆厚労省・全景
先日、厚労省OBの方とお話する機会があり、「医薬品行政の課題」について御見解を伺ったところ、「承認、審査、保険適用の“迅速化”はいうまでもないが、同時に、臨床現場に出た後の評価見直しを“迅速化”することが大事だ」という趣旨の返答があった。新型コロナウイルスのパンデミックで、世界中、大混乱となり、厚労省は「通常承認」よりも提出データ要件が緩い「特例承認」「緊急承認」という枠組みを使って、異例の速さで新たなワクチンや、治療薬の使用を認めてきた。そうしたワクチン、治療薬も臨床現場でデータを積み上げ、新たな知見が出てくる頃だ。しかし、その知見に基づく、
Posted on 8月 30th, 2024 by IDAKA
 自民党総裁選が、9月12日告示、27日投票と決まった。今の日本は自民党総裁=内閣総理大臣なので、国の行く末を左右する重要な「節目」になる。立候補者は現時点で9人と目され、過去最高。「乱立」と揶揄されているが、それだけ意欲ある人が多く、かつ党内論議に幅があるとも言える。悪いことではない。自民の議員か、党員でなければ投票権がないが、全国民は注視すべきだろう。しかし、投票まで、もうひと月切っている。自民総裁、すなわち次期総理候補一人一人の実績、思想信条を把握するには残された時間はあまりに少ない。どうすればいいか?考えたあげく、かつて高名なジャーナリスト、田原総一郎氏が「総理になるなら本を書け!」と言っていたのを思い出し、大型書店に走った(ネットでもいいが、私は書店がスキンなので。。。)。結果、立候補者として名が挙がっている方々のうち、ここ数カ月間で出た新刊本が見つかったのは、石破茂元幹事長と高市早苗経済安全保障担当相の2人だけだった。
自民党総裁選が、9月12日告示、27日投票と決まった。今の日本は自民党総裁=内閣総理大臣なので、国の行く末を左右する重要な「節目」になる。立候補者は現時点で9人と目され、過去最高。「乱立」と揶揄されているが、それだけ意欲ある人が多く、かつ党内論議に幅があるとも言える。悪いことではない。自民の議員か、党員でなければ投票権がないが、全国民は注視すべきだろう。しかし、投票まで、もうひと月切っている。自民総裁、すなわち次期総理候補一人一人の実績、思想信条を把握するには残された時間はあまりに少ない。どうすればいいか?考えたあげく、かつて高名なジャーナリスト、田原総一郎氏が「総理になるなら本を書け!」と言っていたのを思い出し、大型書店に走った(ネットでもいいが、私は書店がスキンなので。。。)。結果、立候補者として名が挙がっている方々のうち、ここ数カ月間で出た新刊本が見つかったのは、石破茂元幹事長と高市早苗経済安全保障担当相の2人だけだった。
Posted on 8月 27th, 2024 by IDAKA

◆東京品川で開かれたMR認定センターの説明会(8月23日)
26年にMR認定制度が変わる。将来、MRになりたいと考えている人、いま現役で将来もMRを続けたいと考えている人、いずれも今以上に主体性を発揮しないと認定を取得できないし、更新されない。MR認定の前提条件である「基礎教育」の合格証取得が、企業ではなく個人の意思に委ねられることになるからだ。企業に「おんぶにだっこ」の時代は終わったのだ。
Posted on 8月 23rd, 2024 by IDAKA

◆武見敬三厚労相
産業構造改革に向けた後発医薬品業界の動きが活発化してきた。秋以降、さらに踏み込んだ議論、動きが各所に出てくるだろう。ただ、武見敬三厚労相の期待と、団体レベル、個社レベルの取り組みは微妙に異なって見える。ここでその違いを、整理しておきたい。
Posted on 8月 19th, 2024 by IDAKA

◆厚労省の全景
今回は、前回(8月14日発)の続き。2025年度の薬価改定(いわゆる中間年改定)はどうなるかーー?。議論の主戦場、中央社会保険医療協議会・薬価専門部会の7月17日と、8月7日の会合を基に、今後の展開を予測する。中間年改定は実質的に薬価の引き下げなので、製薬業界にとって忌むべきことだが、ダメージをできるだけ小さく抑えて、以後の論議を有利に進める「きっかけ」を掴むことはできる。
Posted on 8月 14th, 2024 by IDAKA

◆財務省全景
2025年度の薬価改定(いわゆる中間年改定)はどうなるかーー。年末にかけて議論がヒートアップしていく。その前に改めて論点を整理しておきたい。まずは改定はあるのかないのか、かりにあるとしたら引き下げ条件はどうなるか。そのテーマに切り込む。
Posted on 8月 9th, 2024 by IDAKA

◆住友ファーマの木村徹代表取締役社長
住友ファーマの株価が、新体制を発表した今年5月以降、上昇傾向(8月9月時点)にある。厳しい経営状況中で社長交代を決め、記者会見を複数回開催、メディアの露出度も高い。7月末に発表した第一四半期決算は基幹3製品(前立腺がん薬オルゴビクス、子宮筋腫・内膜症薬マイフェンブリー、過活動膀胱薬ジェムデサ)の米国売上が伸長し、前年同期との比較で赤字額が改善した。株式市場も反応しているようだ。住友ファーマ(株)【4506】:株価・株式情報 – Yahoo!ファイナンス
Posted on 8月 5th, 2024 by IDAKA

◆大塚ホールディングスの樋口達夫代表取締役社長兼CEO
大塚製薬が米国のジュナナ・セラビューティクス(Jnana Therapeutics Inc.)を8億ドルで買収する。買収完了後、開発品の進捗に合わせ最大3億2500万ドルを支払う契約で、総額11億2500万ドルを投ずる。親会社の大塚ホールディングスが2日に発表した。13年に買収した英アステック社の「フラグメント創薬(FBDD)」技術とのシナジー効果で、これまで低分子では困難とされる希少疾患、自己免疫疾患領域で独創的な創薬に挑む。※この原稿は、業界OB「ShinOM」さんにご協力いただきました!
Posted on 8月 1st, 2024 by IDAKA

◆日本イーライリリーのシモーネJ・トムセン代表取締役社長
日本イーライリリーの早期アルツハイマー型認知症(AD)薬ケサンラ(一般名=ドナネマブ)を日本で承認するかどうかー。厚労省の薬事審議会・医薬品第一部会が今日1日の会議(午後16~18時までの予定)で審議する。かりに承認されればエーザイのレケンビ(レカネマブ)に次ぐ2番目の早期AD薬となる。今後、メディアの報道も急増するだろう。しかし、臨床上、どちらがいいかは、まだわからない。脳内に蓄積したアミロイドβ(ADの原因とされるペプチド)に直接関与するという点では同じだが、臨床試験のデザインも、標的も異なる。画期的な新薬は、製薬企業が投じてきた巨額な費用と、研究開発努力の結晶だ。人々の健康と幸福を守る「社会的な資産」とも言える。メディアの扱い次第では、それに水をかける。各社の報道姿勢も問われるだろう。
Posted on 8月 1st, 2024 by IDAKA

◆中外製薬の奥田修代表取締役社長
何歳まで働くか。どんな風に働くかーー。製薬業界人のみならず社会で“働く人“にとって重要なテーマだ。中外製薬は、社としての考え方を明確に示した。2025年1月以降、人事制度を改め、実質的に定年制を廃止する。年齢ではなく「挑戦」と「熱量」によってどれだけ新たな「価値」を創出したかー。その度合いで、社員を評価する。また、リモートワークの価値を認めながら「対面は大事。会って、話して、つながることがイノベーションを起こす土台になると私は信じている」(奥田修代表取締役・社長懇談会=7月29日開催)との考えを表明。「来たくなる本社オフィス」をスローガンに本社を大改修し、社内にカフェや、交流スペースを新設した。






 自民党総裁選が、
自民党総裁選が、