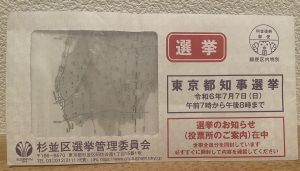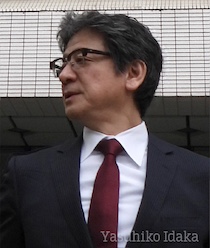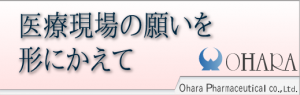Posted on 7月 30th, 2024 by IDAKA

◆中外製薬・奥田修代表取締役社長
中外製薬は、メディア関係者と直接向き合い、近距離で対話する場として、夏に「社長懇談会」、冬に「役員懇談会」というイベントを毎年、開いてくれる。社長懇談会はメディア関係者を4グループに分け午前2回、午後2回、計4回、社長が直接懇談する。役員懇談会はメディア関係者を4つの部屋に誘導、社長と財務(CFO)、研究開発(R&D)と安全性など何人かの担当役員がグループを組んで、メディア関係者が待つ部屋を順番に回って懇談する。私が知る限り、この形式は、同業他社にない。これも「創造で、想像を超える」「ヘルスケア産業のトップイノベーター」を目指す、中外の「独創性」だと思う。
Posted on 7月 24th, 2024 by IDAKA

◆アステラス製薬の河野順コマ―シャルヘッド(グループ取材にて)
医療用医薬品の情報提供体制のあり方がまたひとつ大きな節目を迎えているーー。アステラス製薬が23日に開いたグループ取材でそう感じた。業界のMR数は19年度以降、数千人規模で激減し続けている。各社とも効率化をとことん追求しながら、自社製品のブランド価値を最大限高める新手を練っている。そんな中、アステラスはコマーシャル(営業)部門とメディカルアフェアーズ(MA)部門の「協働」(連携強化)を進める方針を打ち出した。過去約10年、営業とMAは「区分」「区別」が強調され、両部門の距離は遠かった。アステラスは、それを近づけるという。時代は行きつ戻りつ、新陳代謝を繰り返している。
Posted on 7月 22nd, 2024 by IDAKA

◆プレゼンテーションするFRONTEOの守本正宏代表取締役社長
AI(人工知能)を使った新たな治療技術や、医薬品開発(創薬)技術の提供事業が国内でも認められつつある。日本では10年程前から話題にはなっていたが、実証事例がなく医療機関、メーカーは、まだ「半信半疑」だった。しかし、ここ数年、当局の承認を得たAI搭載のプログラム医療機器が続々と登場。製薬企業が創薬に活用して成果を上げるケースも出てきた。自社開発のAIエンジン「KIBIT」(キビット)を持つ日本企業FRONTEOは、医療分野でのAI技術活用、提供サービスに力を入れている企業のひとつだ。最近、メディアやアナリスト向けのイベントを頻繁に開いて、積極的にPRしている。
Posted on 7月 16th, 2024 by IDAKA

◆キエジグループのジャコモ・キエジ取締役 希少疾患事業部門長
新薬の早期導入に向けた日本の前向きな取り組みが、これまで事業実績がない海外製薬企業の新規参入を促すーー。その予兆が早くも出てきた。イタリアの研究開発型バイオ医薬品企業キエジグループの日本法人、キエジ・ファーマ・ジャパンが7月24日から日本で単独事業を開始する。キエジグループのジャコモ・キエジ取締役 希少疾患事業部門長【写真】は7月11日の記者会見で、単独事業を始める理由として「日本市場は米国、中国に次ぎ3番目に大きく、長期に渡って安定している」としたほか、薬事プロセス、患者アクセス、医療保険の償還度合いにおいて「予測可能性が高い」と述べた。
Posted on 7月 12th, 2024 by IDAKA

◆MeijiSeikaファルマの小林大吉郎社長(右)とKMバイオロジクスの永里利秋社長(左)
明治グループの医薬品セグメント、MeijiSeikaファルマ(以下、Meiji)とKMバイオロジクス(同、KM)の事業は、国家戦略に連動するものが多い。とくにここ数年は、その色彩が強まっているように見える。安全保障上の観点から、医療現場で必須の抗菌薬について出発物質、原料の国産化を進めているほか、コロナ感染症パンデミックをきっかけに新型ワクチンの開発に積極化している。また、医薬品安定供給の体制強化に向け、最近、後発医薬品企業の協業(コンソーシアム)を具現化する新会社設立構想を打ち出した。
Posted on 7月 9th, 2024 by IDAKA

厚労省が8日、同省のホームページに「後発医薬品産業の業界再編に関する法令上の懸念点に係る御意見窓口」を設置した。冒頭に「設置趣旨」を表示。医療用医薬品の安定供給には「ある程度大きな規模で生産や品質管理等を行っていく体制」が「有効な選択肢である」と指摘、「企業間の連携・協力や役割分担、コンソーシアムや企業統合など業界再編が行われる機運を高める必要がある」としている。
Posted on 7月 8th, 2024 by IDAKA

◆写真は記事と何ら関係ありません。
東京都知事選、小池百合子氏(71歳、291万超票)が当選しました。次点の石丸伸二氏(41歳、165万票)、3位の蓮舫氏(56歳、128万超票)に大差をつけての“圧勝”でした。国政で支持率に陰りが出ている自民、公明は、わずかながら息を吹き返すでしょう。一方で、立憲民主党など野党の勢いに水を注ぐ結果になった。小池氏優勢は、当初から伝えれていましたが、次点、3位と、これほど大差がつくとは思いませんでした。石丸氏と蓮舫氏の票を合算して、ギリギリ小池氏の票になるくらい。いいか悪いかは別に、これが日本の最大都市、東京の現実ですーー。
Posted on 7月 5th, 2024 by IDAKA
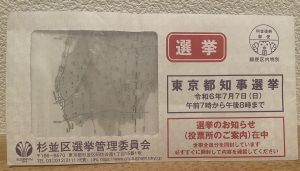
みなさんお元気ですか?
さて東京都知事選の投票まで後2日となりました。告示前、事実上、現職、元衆院議員の小池百合子氏と、前参院議員、蓮舫氏の一騎打ちとなると思われましたが、元広島県安芸高田市長の石丸伸二氏が加わり、現時点での予測上位は「三つ巴」の展開になっています。。自民、公明の後ろ盾を得た小池氏がやや優勢と伝えれ、立民、共産が推す蓮舫氏、自民や日本維新の会の一部に支持者が多い石丸氏が、小池氏を追いかける格好です。立候補者は何と56人で過去最高!!!都政の「カオス」を
Posted on 7月 4th, 2024 by IDAKA

◆ソフトバンクの孫正義代表取締役会長兼社長
ソフトバンクグループ(SBG)が米ベンチャー企業テンパス(Tempus)と組んで、新たなAIデジタル医療サービスを国内で開始する。非識別化(個人が特定できないように処理)した患者の検査データを蓄積。それをAIで解析して、結果情報を提供するサービスだ。収益を見込む第一の顧客ターゲットは、製薬企業。創薬研究、開発での活用を想定している。果たして、どこまで浸透するかーー。日本は海外と比べて医療分野のDX(デジタルトランスフォーメーション)に慎重、中でも患者データが絡む民間事業はレギュレーション(規制)の壁も高い。
Posted on 7月 1st, 2024 by IDAKA

◆武田薬品のクリストフ・ウェバー代表取締役CEO
7月に突入。2024年も半分過ぎた。先週(6月24~28日)は、複数のイベントが重なった。今回は、そのうち武田薬品の株主総会と、住友ファーマの新社長会見を個人的な見解、感想を交えて寸評する。